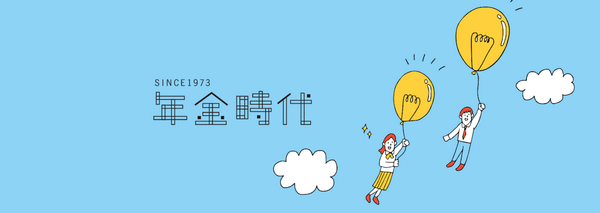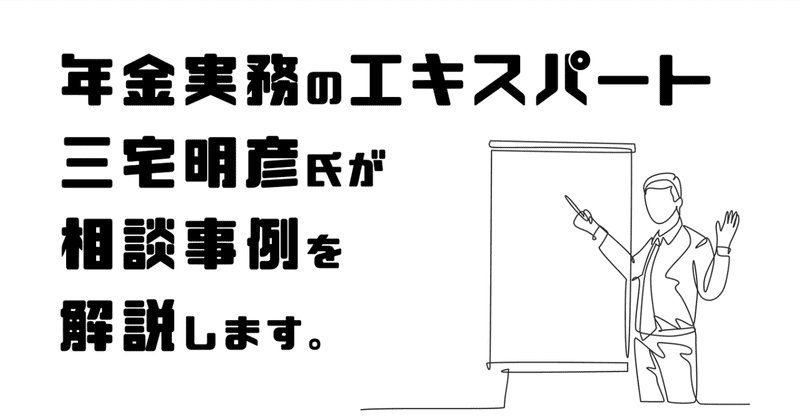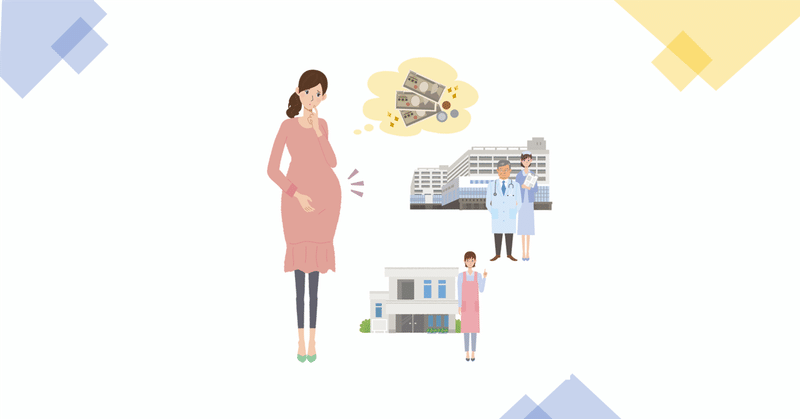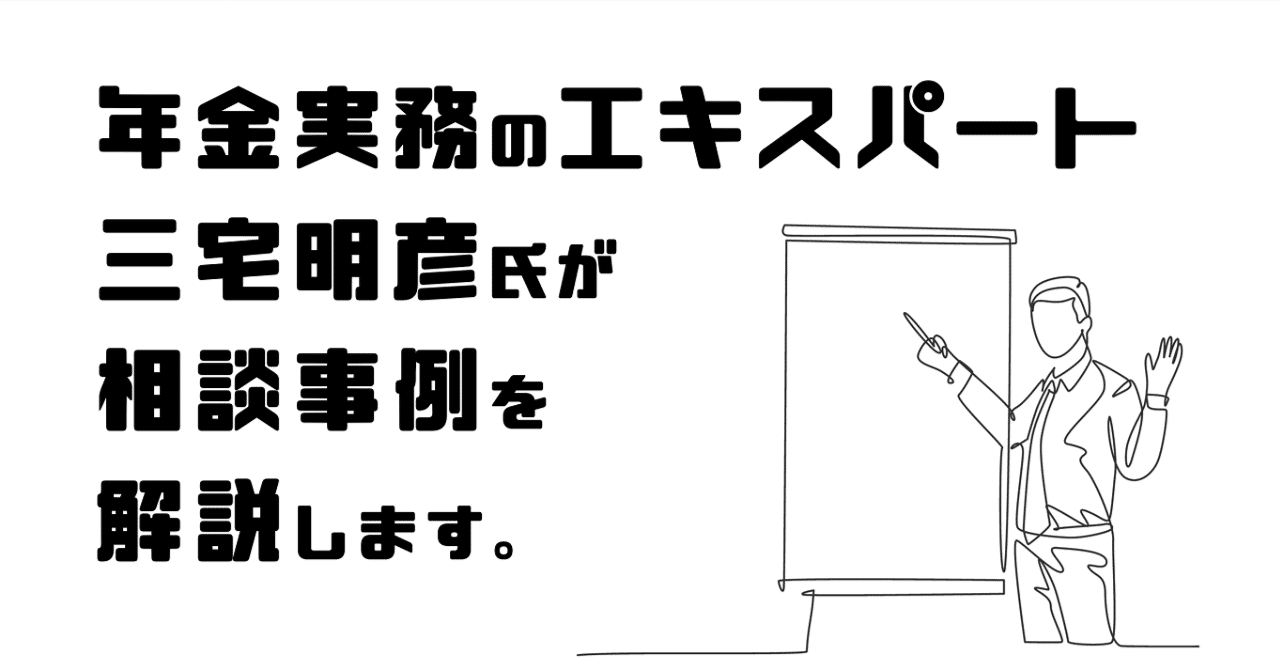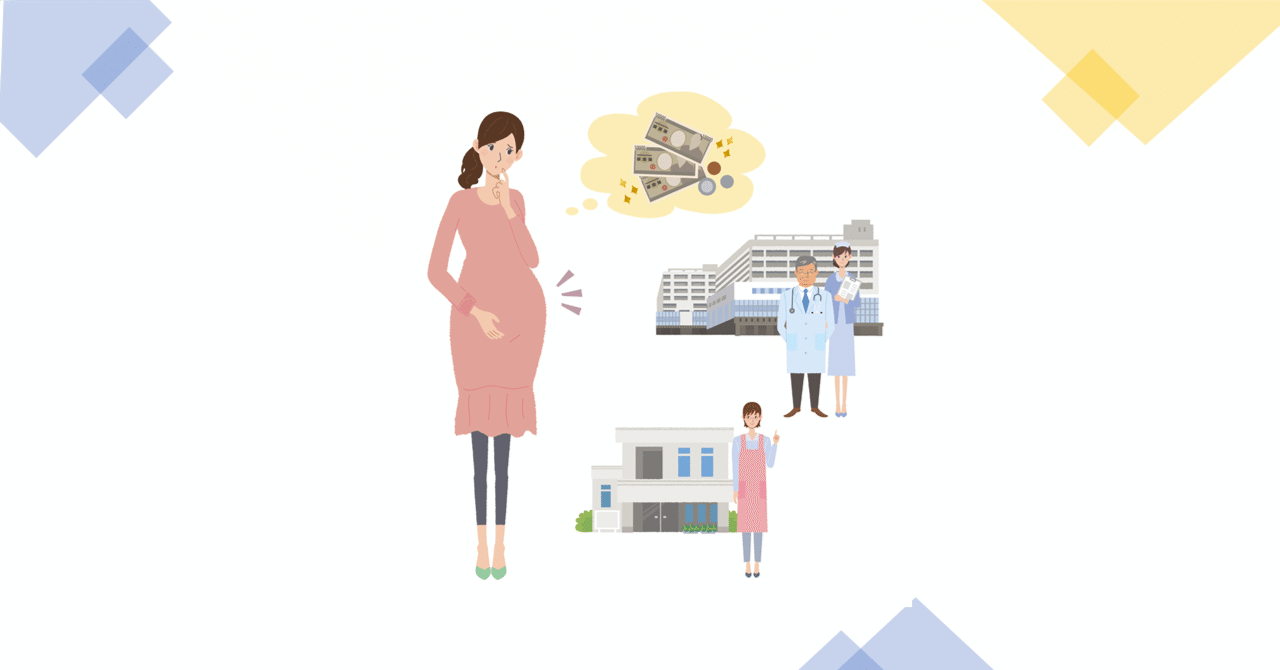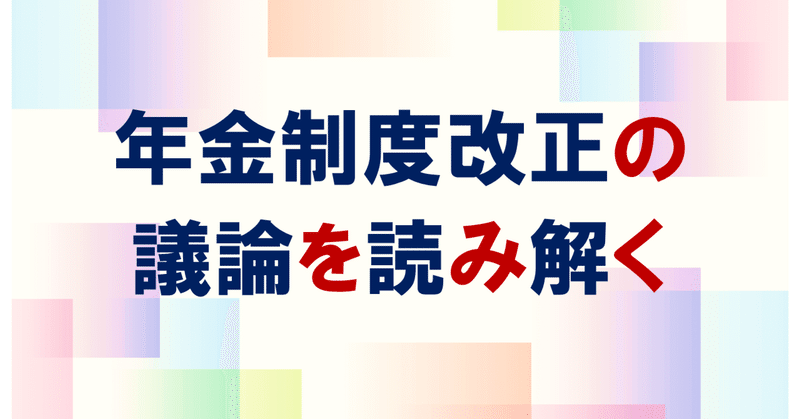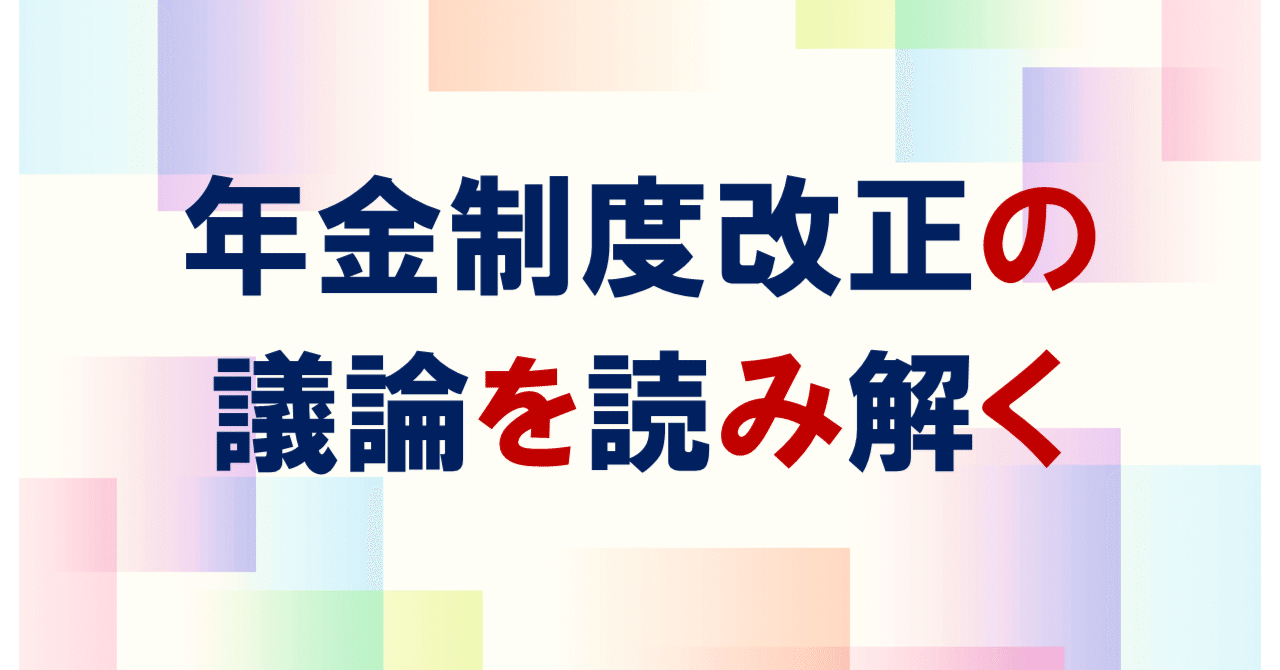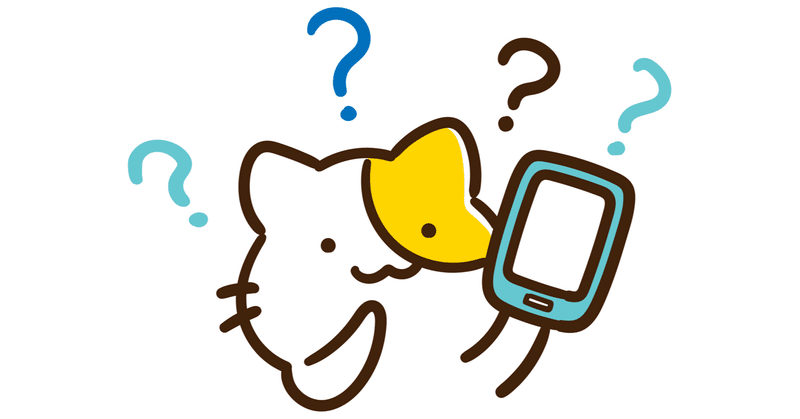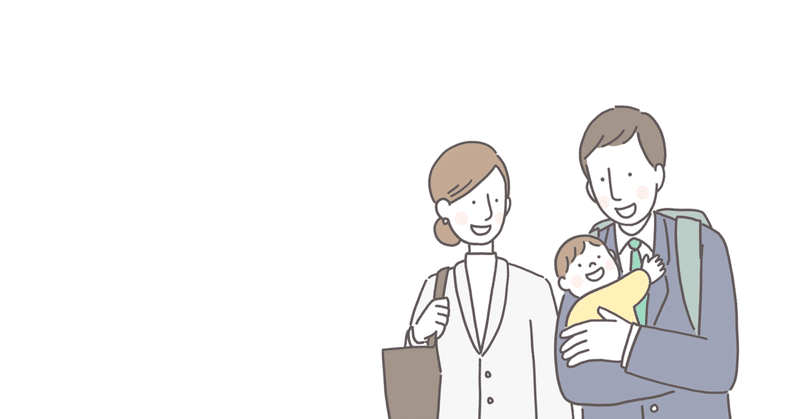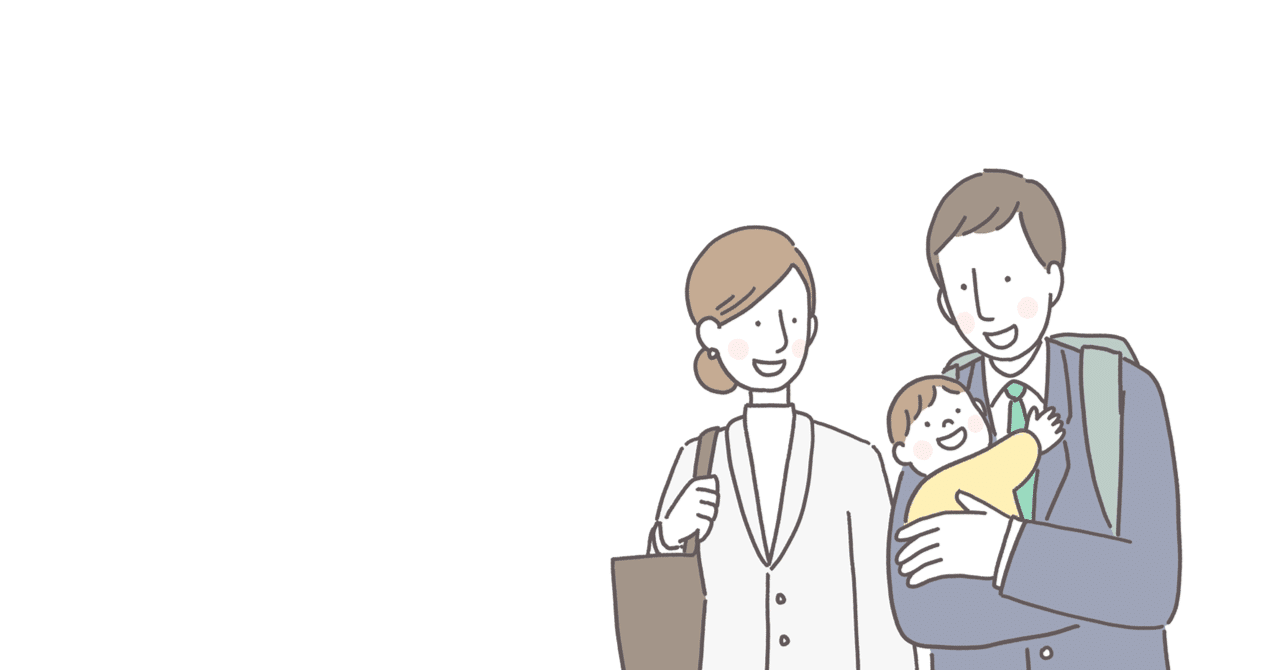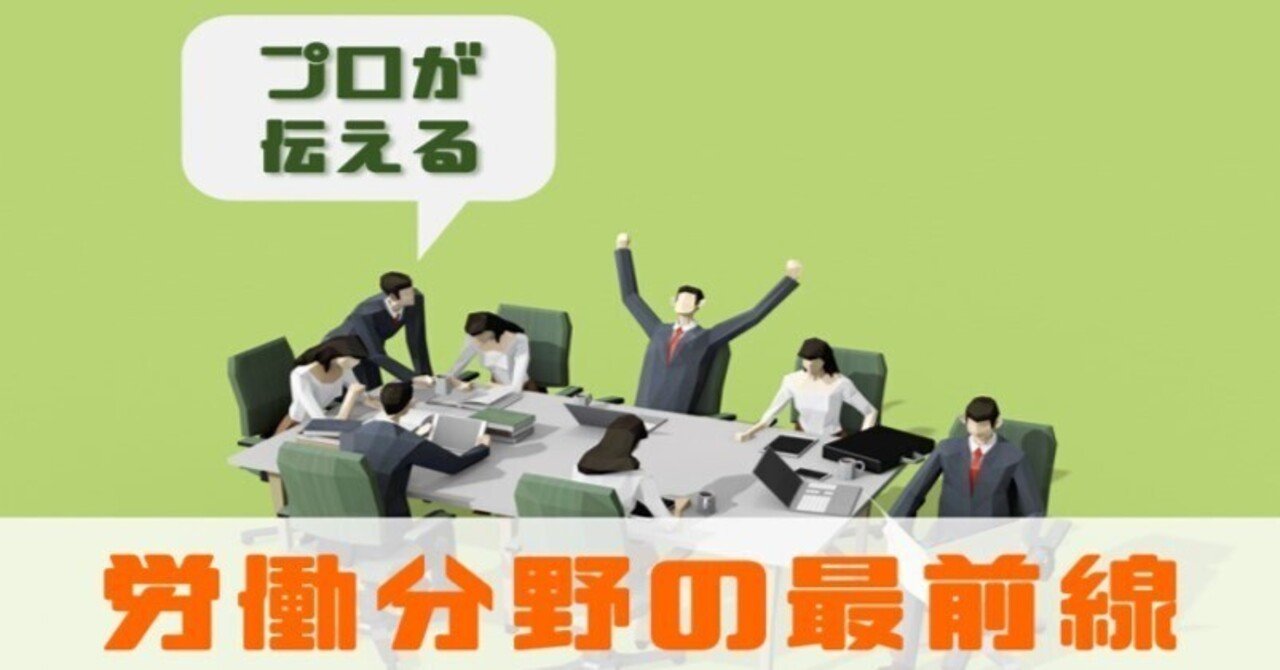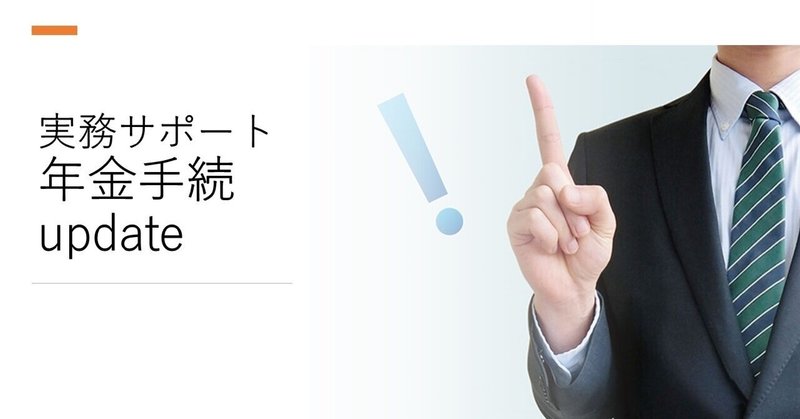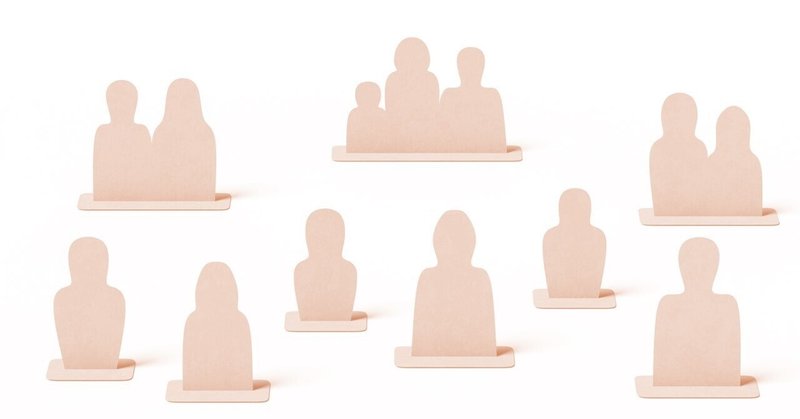最近の記事
- 固定された記事
マガジン
記事

謎の新興国アゼルバイジャンから|#46 「生産性」ってなんでしょう―こんなに長時間労働してるのに給与が上がらない。日本人は働きが悪い?―
香取 照幸(かとり てるゆき)/アゼルバイジャン共和国日本国特命全権大使(原稿執筆当時) みなさんこんにちは。 新しい元号は「令和」になりました。 4月30日にはいよいよ今上天皇陛下が譲位され、5月1日に皇太子殿下が即位されます。 昨年12月のお誕生日の記者会見で、天皇陛下は、 「平成の時代に入り、戦後50年、60年、70年の節目の年を迎えました。先の大戦で多くの人命が失われ、また、我が国の戦後の平和と繁栄が、このような多くの犠牲と国民のたゆみない努力によって築かれたもの
有料100